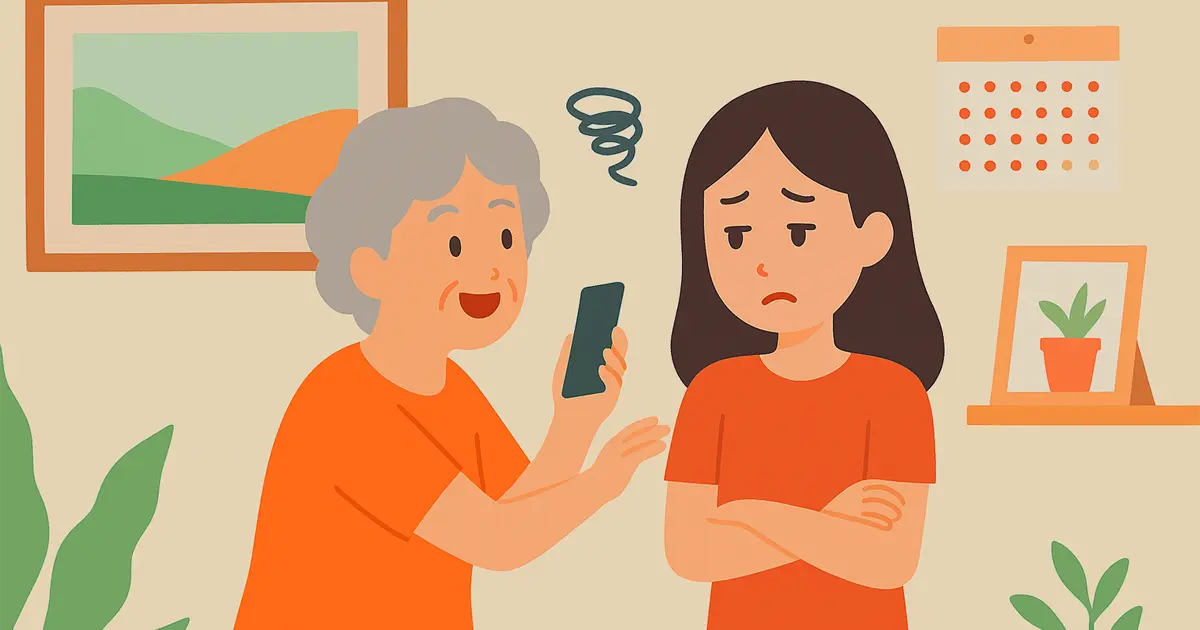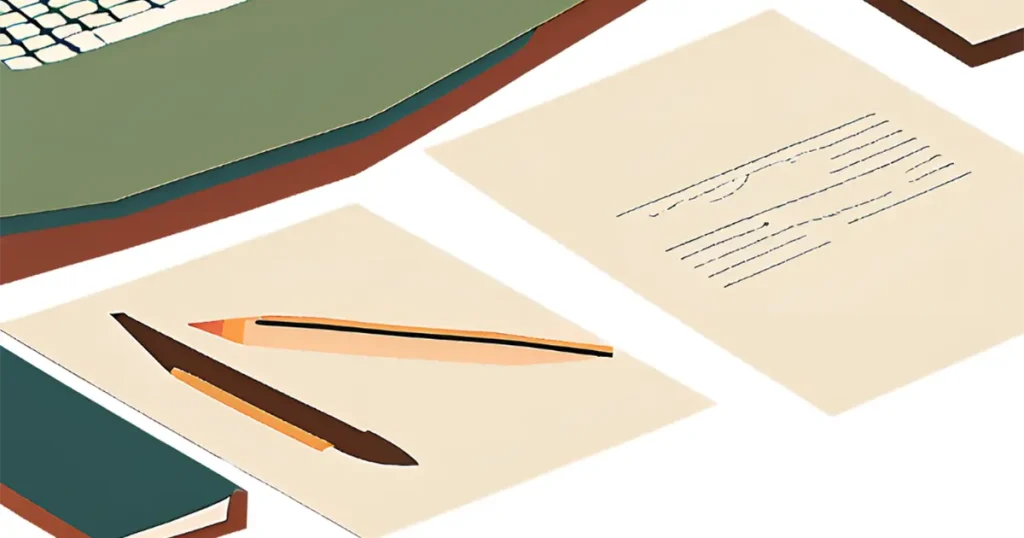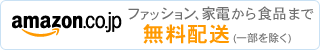「親が急に構ってほしがるようになった…」そんな変化に戸惑うことはありませんか?
「まだ、そんなことないよ!」という方も、親が年齢を重ねれば、そんな兆しが見えてくるかもしれません…。だからちょっと聞いておいてくださいね!
実は親が、「親が急に構ってほしがるようになった…」その裏側には、寂しさや不安が隠れていることが多いのです……。放っておくと親子関係がギクシャクしてしまうことも少なくないいですよ!
でも、ほんの少しの関わり方を工夫するだけで、お互いが安心できる時間に変ることもできるんです。本記事では、親の「構ってちゃん」行動を理解し、負担にならずに寄り添う方法を具体的に解説していきますね!
「構ってちゃん」は寂しさのサイン|その背景にある親の気持ち
親が年齢を重ねると、「電話を毎日かけてくる」「ちょっとしたことで頼ってくる」など、子どもに対して“構ってほしい”行動を見せることがあります。実はそれは単なるわがままではなく、心の奥にある 「寂しさのサイン」 かもしれないのです……。
なぜなら、人は年齢を重ねるにつれて環境が変わり、以前のように誰かと自然に関わる機会が減ってしまっているからなんですね!
だから、「構ってちゃん」に見える行動の裏には、親なりの必死な気持ちが隠れているわけです・・・。
親が「構ってちゃん」になる背景
📌 親が寂しさを感じやすくなる理由には、いくつかの共通点があります。
- 退職して、社会とのつながりが減った
- 配偶者や友人との別れが増えてきた
- 健康面の不安を抱えている
- 自分の存在意義を見失いやすい
こうして見ると、「ちょっとかまってほしい」というサインは自然な流れとも言えるんです。
行動の裏にある親の本音
「なんでそんなに電話ばかり?」と思うこともあるでしょう。でも、その行動をよく観察してみてください。
📌 こんな気持ちが隠れている場合が多いんです。
| 親の行動 | 背景にある本音 |
|---|---|
| 毎日電話をしてくる | 孤独感を埋めたい、声を聞くだけで安心する |
| ささいな頼みごとを繰り返す | 誰かに必要とされたい |
| 体調の不安を何度も話す | 共感してほしい、安心を分けてもらいたい |
| 昔話を何度もする | 自分の存在を確かめたい、記憶を共有したい |
親が見せる行動は「私の気持ちに気づいてほしい」というメッセージなんですね。
ワンポイントアドバイス
「構ってちゃん」に見える行動も、実は愛情の裏返しでもあるわけです。だから、イライラして突き放すよりも「寂しいんだな」と受け止めてあげることが大切です…。ただ、全部に応える必要はありませんよ!
- 今日は5分だけ電話する
- 週に一度は顔を見せる
- 「ありがとう」の言葉を意識して伝える
こうした小さな積み重ねで、親は安心を得て、子どもも無理なく関われるようになりますから・・・。

寄り添う前に|まずは「自分の心」を整えることから
親の「構ってちゃん」な行動に向き合うとき、つい感情的になったり疲れてしまうことがあります。
でも、寄り添う前に大事なのは 「自分の心を整えること」 なんです。それは、自分自身が落ち着いていなければ、親の不安や寂しさに振り回されやすくなるからです。つまり、まずは自分が安心できる状態をつくることが、親との関係を良い方向へ導く近道なんですね・・・。
心を整えるためのステップ
自分を落ち着かせる方法は難しいものではありません・・・。
📌 ちょっとした工夫で、気持ちはずいぶんと楽になれます・・・。
- 深呼吸をして気持ちをリセットする
- 「今日は5分だけ話そう」と時間の枠を決める
- 趣味や運動でストレスを解消する
- 自分の頑張りをちゃんと認める
自分の心を守ることは、親との関わりを長く続けていくための土台になるんです。
親と向き合う前の「心の準備」
📌 「寄り添うぞ!」と意気込む前に、心の余裕を確認するのも大切です。
| チェック項目 | 状態の目安 |
|---|---|
| 最近イライラが多い | 自分の休養が足りていないサイン |
| 親の話を聞くと疲れが増す | 無理に応じすぎている可能性 |
| 「また電話か…」とため息が出る | 関係の距離感を見直す時期 |
| 親と話しても気持ちが安定している | 心の準備が整っている証拠 |
自分の状態を振り返るだけでも「今どんな心で向き合っているか」に気づけますよね。
ワンポイントアドバイス
📌 もし「ちょっと疲れているな」と感じたら、無理に応えなくても大丈夫です。
- 「今日は忙しいから、また明日ね」と短く伝える
- 電話を一度出ないで、あとで折り返す
- 第三者(きょうだいや友人)に気持ちをシェアする
こうした工夫で、あなた自身の気持ちが守られますし、親も「無理に構ってもらっている」空気を感じなくなるんです。

5分でできること|毎日続ける「ちょこっとコミュニケーション」
親との関係を良くしたいと思っても、「長時間一緒に過ごすのは難しい」と感じる方は多いものです。
そんな時のポイントは、 短くても“毎日続ける”コミュニケーション なんです。なぜなら、たった数分でも「気にかけてもらえている」という実感は、親の安心感につながるからです。つまり、無理のないペースで続けられる“ちょこっと習慣”こそが、親子の絆を深める近道なんですね。
毎日できる「ちょこっと声かけ」
📌 時間はほんの3〜5分でも大丈夫。むしろ「短いけれど毎日」がポイントです。
- 「今日は体調どう?」と聞いてみる
- 「昨日のテレビ、面白かったね」と共通の話題をふる
- 「ありがとう」「助かったよ」と一言伝える
- 季節や天気の話を軽くする
こうした短いやりとりは、親にとって「忘れられていない」という安心感になるんですよ。
ちょこっと習慣を無理なく続ける工夫
📌 忙しい毎日の中でも取り入れやすいように、「ながら」でもできる工夫がおすすめです。
| シーン | できる声かけ |
|---|---|
| 朝の挨拶 | 「よく眠れた?」と一言添える |
| 食事のとき | 「これ、美味しいね」と感想をシェアする |
| 外出前 | 「行ってきます、気をつけてね」と声をかける |
| 夜のひととき | 「今日はこんなことがあったよ」と話題を分け合う |
こうして見ると、特別な準備がなくても自然に続けられるんです。
ワンポイントアドバイス
「毎日話題を探すのは大変そう…」と思うかもしれませんね。そんなときは、決まったフレーズを“合言葉”にするのがおすすめです。
たとえば「おはよう!元気?」や「ありがとうね」。同じ言葉でも繰り返すことで、親は「毎日声をかけてもらえる」という安心を感じるんです。
つまり、親との関係を育むのに必要なのは「長時間」よりも「毎日のちょっとずつ」なんです。3分でも5分でもいいから、小さな会話を積み重ねてみましょう。気づいたら、それが親の心を支える大きな力になっているはずですよ。
こんな記事も読んでみてね!
小さな「ありがとう」を習慣に|親の自己肯定感を満たす関わり方
誰でも年齢を重ねると、どうしても「自分はもう役に立っていないのでは…」という気持ちを抱きやすくなるものです。
そんなときに大きな支えになるのが、身近な人からの「ありがとう」の一言です。つまり、感謝の言葉は、親にとって自分の存在価値を再確認できる“心の栄養”なんですね。
「ありがとう」が持つ力
「ありがとう」には、ただの挨拶以上の力があります。なぜなら、感謝の言葉をかけられることで、親は「自分が誰かの役に立てている」と感じられるからです。
📌 こんな小さな場面でも効果的なんですよ。
- ご飯を作ってくれたときに「美味しかったよ、ありがとう」
- お茶を出してくれたときに「気がきくね、助かるよ」
- ちょっとした手伝いをしてもらったときに「ありがたいなぁ」
こうして見ると、特別な出来事じゃなくても、感謝は日常にたくさん隠れているんです。
習慣にするための工夫
「ありがとう」を自然に口にできるようにするには、生活の中で“決まった場面”を持つのが続けやすいコツです。
| タイミング | 感謝の伝え方 |
|---|---|
| 朝の挨拶 | 「今日も起こしてくれてありがとう」 |
| 食事のあと | 「おいしかった!ごちそうさま」 |
| 外出時 | 「行ってきます。いつも見送ってくれてありがとう」 |
| 就寝前 | 「今日も一日ありがとう。おやすみ」 |
習慣化のカギは「当たり前の中に感謝を差し込むこと」なんですね!
ワンポイントアドバイス
もし口に出すのが恥ずかしいときは、メモやLINEで伝える方法もあります。短い言葉でも書き残すことで、「大切に思ってくれている」と実感できるんです。実はそれだけでも十分効果がありますよ。
「ありがとう」を日々の中で繰り返すことが、親の自己肯定感を満たす一番シンプルで強力な方法なんです。小さな一言が積み重なれば、「まだまだ自分も大事にされている」という安心感につながります。だからこそ、無理のない形で“感謝の習慣”を取り入れてみてくださいね。


一緒に楽しむ時間を作ろう|共通の趣味や思い出を増やす
親との関係がぎくしゃくするとき、つい「どう接すればいいんだろう…」と悩みがち・・・。
でも、意外にも解決のヒントは「一緒に楽しむ時間」を増やすことにあります。なぜなら、楽しさを共有することで、自然と会話が生まれ、心の距離が近づくからです。つまり、共通の体験こそが信頼関係を深める近道だったわけです……。
共通の楽しみが生むもの
一緒に過ごす時間は、ただの暇つぶしではありません。
📌 そこから次のような効果が得られるんです。
- 話題が自然に広がる
- 「一緒に笑う」ことで安心感が生まれる
- 親も「まだ楽しめる」と感じられる
- 子ども側も「無理して構う」から「自然に楽しむ」へ変わる
そうなんです!共通の趣味や思い出づくりは、お互いの負担を減らしてくれるんですよ。
どんな楽しみ方がある?
📌 楽しみ方は人それぞれですが、「親も子も気軽にできること」が続けやすいポイントです。
| ジャンル | 具体例 |
|---|---|
| 趣味系 | ガーデニング・写真・料理・手芸 |
| おでかけ系 | 近所の散歩・季節の花見・地域のイベント参加 |
| 家の中で | 昔のアルバムを一緒に見る・テレビ番組を一緒に観賞 |
| 新しいこと | 簡単なスマホ操作を教え合う・オンライン講座を体験 |
こうして見ると、特別な準備がなくても「楽しみの種」は日常に転がっているんですよね。
ワンポイントアドバイス
「共通の趣味がない」と思っている場合でも大丈夫・・・。実は、“親の得意なことを子が学ぶ”スタイルにすると自然に会話が広がるんです。例えば、母のレシピを教わったり、父の昔の仕事話を聞いたりするだけでも「一緒に取り組んでいる感覚」が生まれますよ。


新しい「居場所」を提案する|社会とのつながりをサポートする
親が「構ってちゃん」になってしまう背景には、家庭以外で安心して過ごせる場が少なくなっている、という事情もあります。言い方を変えれば、「自分の居場所が欲しい」という自然な気持ちなんですね。だからこそ、家族以外のつながりを広げることが、親の心を豊かにしてくれるんです。
なぜ「居場所」が大事なのか
年齢を重ねると、仕事や役割が減り、人と会う機会が少なくなっていきます。その結果、家族に依存してしまうこともあるんです。
📌 でも新しい居場所を見つけると――
- 毎日の楽しみが増える
- 同じ立場の仲間と気持ちを分かち合える
- 孤独感が和らぐ
- 家族に対する「構って」も和らぐ
そうなんです! 居場所があるだけで心の安定が生まれるんですよ。
居場所づくりのアイデア
📌 「居場所」といっても大げさなものではなく、小さな交流の積み重ねで十分です。
| 種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 地域のつながり | 健康体操・公民館サークル・自治体のイベント |
| 趣味を共有 | 写真・園芸・手芸・料理教室 |
| ボランティア | 子ども見守り・清掃活動・語り部活動 |
| オンライン | 趣味の掲示板・オンライン講座・ビデオ通話 |
こうして見ると、身近なところに「参加できる場所」が意外とたくさんあるんです。
家族ができるサポート
親が自分から動き出すのは、ちょっと勇気がいることです。
📌 だから家族のサポートが背中を押す役割になるんですよ。
- 情報を一緒に探す
- 初めての参加に付き添う
- 無理にすすめず「気になる?」と声をかける
- 体験後に感想を聞いて共感する
こうした小さな働きかけが、「行ってみようかな」という気持ちにつながるんです。
ワンポイントアドバイス
「居場所を見つける」と聞くと、何か大きな決断のように思いがちですが、実は “お試し感覚で行ってみる” くらいがちょうどいいんです。つまり、「合わなければやめてもいい」という気持ちで大丈夫なんですね! 気軽さが続けるコツになるんです…。
こんな記事も読んでみてね!
専門家やサービスに頼る|一人で抱え込まないための選択肢
親の「構ってちゃん」な言動に、どう応えていいかわからず、つい一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。でも実は、すべてを家族だけで解決する必要はないんです。なぜなら、専門家や地域のサービスを上手に活用することで、親も家族もずっとラクになれるからです。辛ければ、「頼ること」そのものが前向きな選択肢なんですよ。
どんなサポートがあるの?
📌 一口に「専門家やサービス」といっても、実は幅広いんです。
| サポートの種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 医療・心理 | 心療内科・カウンセリング・精神保健福祉センター |
| 介護・福祉 | デイサービス・訪問介護・地域包括支援センター |
| コミュニティ | シニアサークル・ボランティア活動の紹介 |
| 家族支援 | 介護者相談窓口・オンライン相談サービス |
相談することのメリット
「知らない人に話すなんて…」と最初は抵抗があるかもしれません。
📌 けれど、実際には次のようなメリットがあるんですよ。
- 客観的なアドバイスがもらえる
- 家族以外の「聞き役」ができる
- 必要な制度や支援がわかる
- 家族の気持ちも整理できる
つまり、専門家は「親のため」だけでなく、「支える側のあなた」の味方にもなってくれるんです。
どうやって始めればいい?
📌 最初の一歩は、とてもシンプルで大丈夫です。
- 地域包括支援センターに電話してみる
- 市区町村の高齢者支援課に相談する
- 主治医に「相談できる窓口はありますか?」と聞く
- ネットで「親 相談 窓口」と検索する
どれも「ちょっと聞いてみる」だけで十分なスタートなんですよ。
ワンポイントアドバイス
「専門家に頼るのは、弱さではないかな…」と感じる方もいます。でも、要するにそれって 家族を守るための“賢い工夫” なんです。だから安心して、まずは気軽に相談してみましょうね。
外の力を借りることは、親の安心だけでなく、家族みんなの笑顔を増やす近道なんです。無理に全部を抱え込まず、「頼れるところに頼る」ことで、日常はもっとやさしいものになっていきますよ。


「構ってちゃん」になった親|そんな子供も体験談
毎日かかってくる「用もない電話」|息子を困らせた母の行動
仕事の合間に、母からの電話が毎日のように鳴る。内容は「今日の天気知ってる?」「ご飯何食べた?」と些細なものばかり。最初は笑って対応していたが、次第に「またか…」と気持ちが重くなっていった。ある日、思い切って「お母さん、電話は嬉しいけど、仕事中は困るんだ。夜に10分だけ話す時間を作ろう」と提案。すると母は最初こそ拗ねたが、やがて「その時間を楽しみにしてる」と言うようになった。母の「構って」が「楽しみ」に変わった瞬間だった。
LINEの絵文字攻撃|娘を振り回す父のメッセージ
70代の父はスマホを覚えてから毎日LINEを送ってくる。しかも絵文字やスタンプだらけで、読むのが一苦労。最初は「うるさいなあ」と思っていたが、父の孤独感から来るものだと気づいた。そこで娘は「毎朝一言、今日の気分を送って」とルールを作り、代わりに娘も「おはよう」と返すことに。父は次第に落ち着き、やたらとスタンプを送ることも減った。親子のやり取りが「負担」から「日課」になったことで、関係が和らいだ。
家に押しかけてくる母|夫婦生活との板挟み
結婚後も「寂しい」と母が頻繁に家へ来るようになった。最初は夫も笑顔で迎えていたが、次第に「落ち着かない」と不満をこぼすように。娘は悩んだ末、「週に一度だけ一緒に夕飯を食べる」というルールを提案。母には「私も夫と過ごす時間が大事なの」と伝えると、母は意外にもあっさり納得した。それ以来、母はその「特別な日」を楽しみにし、夫婦の時間も守られるようになった。
孫への執着|祖母と母の葛藤
70歳の母は、孫に会いたくて毎日のように「遊びに行っていい?」と連絡してきた。最初は微笑ましかったが、子育てで疲れている娘にとっては負担に。ある日、娘は「毎週土曜の午前中なら一緒に遊べる」と提案。さらに孫と母が一緒に楽しめる「折り紙クラブ」を地域で探してあげた。母はそこで同世代の仲間を見つけ、孫に執着する頻度が減った。娘も「母の世界が広がった」と安心できた。
アドバイス: 親の「構って」は、時に「社会とのつながり不足」から来ています。新しい居場所を見つけてあげましょう。


「構ってちゃん」は卒業できる|親も自分も笑顔になる未来へ
親の「構ってちゃん」な言動は、寂しさや不安から生まれる自然なサインでした。けれど、ここまでお伝えした工夫を少しずつ取り入れることで、その姿は少しずつ変わっていくんです。つまり、「構ってちゃん」状態は永遠ではなく、卒業できるものなんですよ・・・。
卒業に近づくサインとは?
どんな変化があれば「前に進めている」といえるのでしょうか?
📌 目に見えるサインを表にまとめてみました。
| 以前の状態 | 卒業に近づいた状態 |
|---|---|
| 電話やLINEが頻繁すぎる | 必要なときだけ、安心して連絡してくる |
| 愚痴が中心 | 近況や楽しい出来事を話してくれる |
| 外出に消極的 | 趣味やサークルに前向きに参加する |
| 「ひとりは寂しい」が口癖 | 「今日はゆっくりできてよかった」と言える |
こうして見ると、少しずつでも確実に前向きな変化が見えてくるんです。
家族も一緒に成長できる
📌 親の変化は、同時に家族にとっても大切な成長になります。
- 「無理に応えなくていい」と気づける
- サポートのバランスを整えられる
- 親との時間を前より穏やかに楽しめる
つまり、親だけでなく家族全体が笑顔になれる未来につながるんです。
笑顔の未来を描こう
「構ってちゃん」を卒業できた親は、ただ落ち着くだけでなく、新しい楽しみや生きがいを見つけていきます。そしてその姿を見るあなた自身も、安心して自分の時間を過ごせるようになるんです。
だからこそ、焦らず一歩ずつで大丈夫。小さな積み重ねが、親も自分も笑顔になれる未来を作っていくんです。
ワンポイントアドバイス
「卒業」という言葉は大げさに感じるかもしれません。でも大切なのは、完璧に変えることではなく、小さな前進を見つけて喜ぶこと です。昨日より少しラクに会話できた、それだけでも十分な一歩ではないでしょうか!
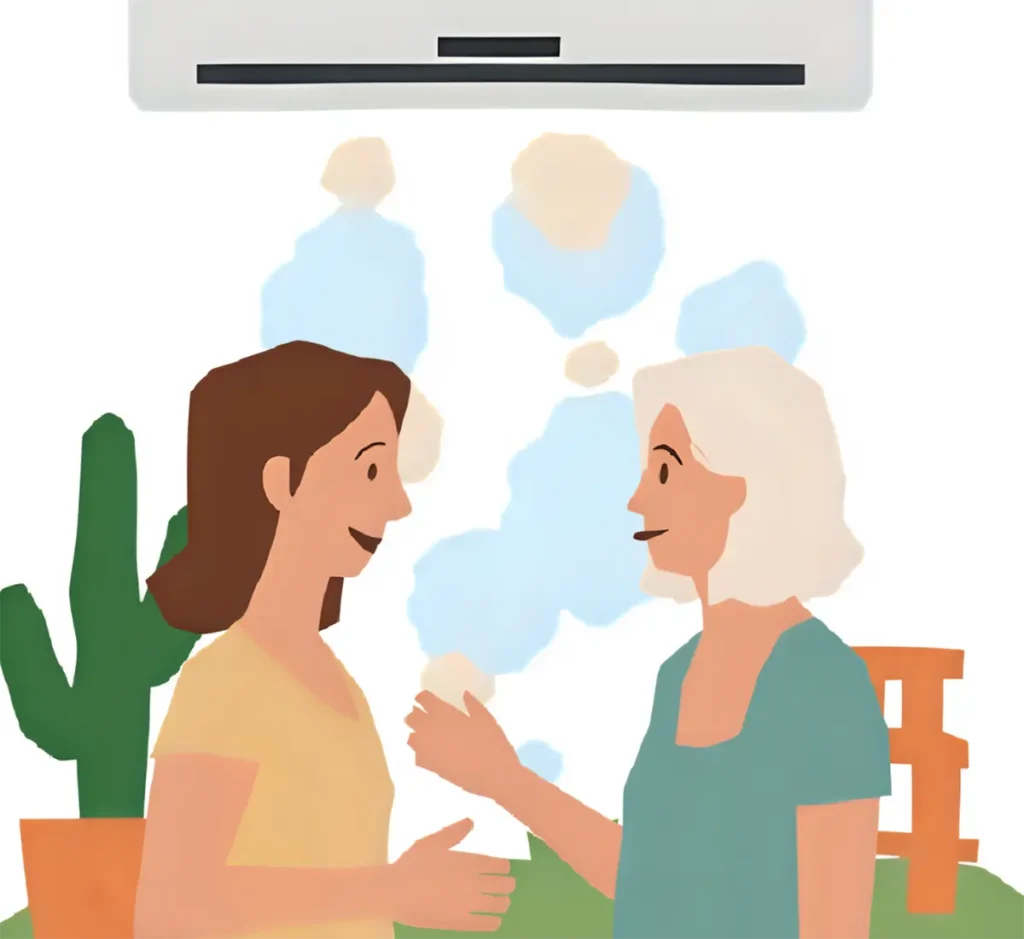
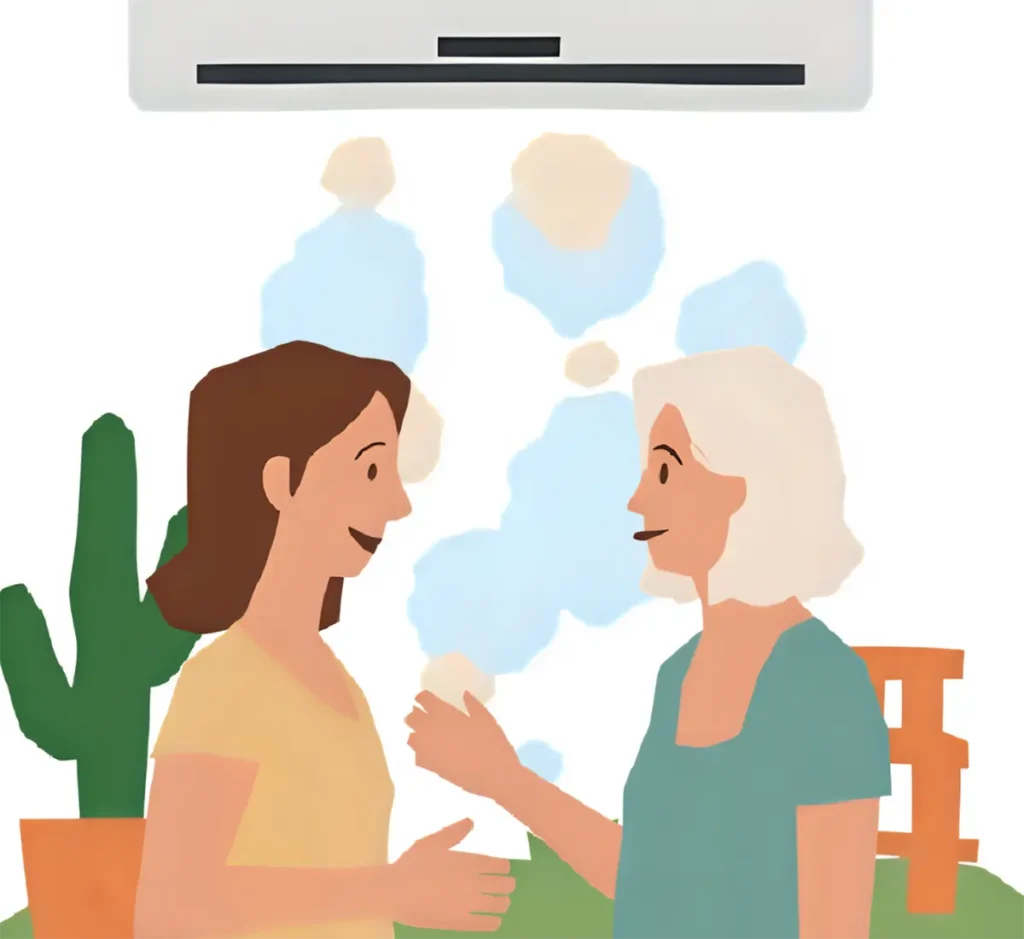
親が「構ってちゃん」になったらで よくあるQ&A
親が「構ってちゃん」になるのは、ただわがままなのではなく、寂しさや安心を求めるサインです。大切なのは、自分自身の心を整えたうえで、小さな声かけや「ありがとう」といった日常の積み重ねを意識すること……。共通の趣味や楽しい時間を共有すれば、親子関係はぐっと温かいものになります。
また、社会とのつながりを持てる居場所を提案したり、必要に応じて専門家に相談するのも立派なサポートです。すべてを一人で背負う必要はありません。親も自分も心地よく過ごせる関係を築けば、「構ってちゃん」の姿は少しずつ変化し、笑顔が増える未来へとつながっていくのです。
「それ、40代ではNGかも?」——今さら聞けない“大人のマナー”、ちゃんと身についていますか?
年齢を重ねるごとに、周囲の見る目も自然と変わってくるもの。ビジネスでもプライベートでも、ちょっとした振る舞いがあなたの印象を大きく左右します。
「え、そんなこともマナーなの?」と思わずドキッとする内容も盛りだくさん!
40代の今だからこそ押さえておきたいマナーをわかりやすくまとめました。
気になる方は、こちらの記事をぜひ読んでみてくださいね。