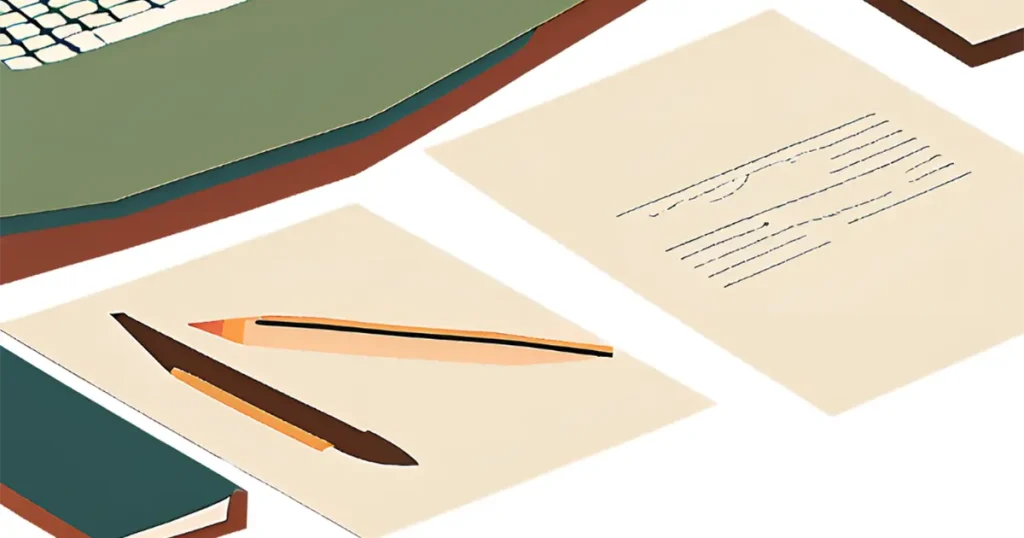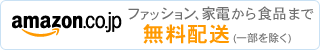40代は仕事も家庭もまさに「責任世代」…。しかし、もし突然の病気やケガで働けなくなったら──。収入が止まり、生活が一変するリスクは誰にでも起こり得ます。そんなときに頼れるのが「守りの保険」…。医療費や生活費の不安をぐっと減らし、家族の安心を守るための大切な備えです。
本記事では、医療保険・就業不能保険・がん保険などを中心に、40代が今見直すべきポイントを徹底解説します。未来への安心を、今ここから始めましょうね!
なぜ40代は「守りの保険」が必要なのか|働き盛りこそリスクに備える
40代の皆さんは、まさに人生の充実期ですね!キャリアも家庭も、一番の頑張りどころだと思います。ただ、そんな「働き盛り」の時期だからこそ、万が一のことがあったときに家族とご自身の生活を守るための「守りの保険」が、とても重要になるんですね!。今、しっかりと備えることが、未来の安心につながる…そう考えると、なんだか前向きな気持ちになりませんか?
40代が抱える「リスクの最大化」とは
40代は、ご自身の体力の変化はもちろん、家庭や仕事においても、リスクが一番大きくなる時期だと言えます。それは、「責任」と「支出」が最も高まるからです。
| 項目 | 40代で高まるもの | リスクの具体的な例 |
|---|---|---|
| 責任 | 家族(子育て、親の介護)、仕事の役職 | 収入の途絶、医療費の発生 |
| 支出 | 住宅ローン、教育費(塾、大学準備)、生活費 | 貯蓄の取り崩し、家計の破綻 |
これらの重荷がある中で、ご自身が病気やケガで倒れてしまうと、その影響はご家族全体に及んでしまうんですね。だからこそ、そういった大きなリスクから「生活基盤」を守るための備えが必要になるんです。
攻めではなく「守り」に徹する保険の役割
保険には大きく分けて「攻めの保険(貯蓄型)」と「守りの保険(保障型)」がありますが、今の40代に必要なのは、何よりも「守りの保険」です。守りの保険は、病気やケガといった「予測できない大きな出費や収入減」から家計を守ることを目的としています。
📌 具体的に、守りの保険が40代の生活を守る主なポイントは以下の3つです。
- 収入のカバー
- 病気やケガで長期間働けなくなったとき、毎月の生活費を保険で補うことができます。住宅ローンや教育費を心配せずに、治療に専念できる安心感が生まれます。
- 医療費のサポート
- 高額になりがちな入院費や手術費、先進医療の費用などをカバーし、貯蓄を崩さずに済みます。
- 精神的な安定
- 「万が一の備えがある」という事実そのものが、日々の安心感につながります。前向きに仕事や子育てに取り組むための、大きな心の支えになるんですね。
「守りの保険」は、例えるならご家族の生活を守るための強力な「防護服」なんです。この防護服があるからこそ、40代の皆さんは、日々の生活を前向きに、そして安心して送ることができるようになるんです。
ライフステージの変化と保険の見直し
40代は、人生の中でもライフステージが大きく変化する時期…。「過去の保険のままで大丈夫?」と問いかけてみる良い機会です。
- 独身時代に加入した保険のまま、扶養する家族が増えていませんか?
- 住宅ローンを組み、必要な死亡保障額が変わっていませんか?
- 健康状態の変化で、必要な医療保障の範囲が変わっていませんか?
たとえば、昔加入した医療保険は、「入院日数が長期化」する時代に合わせて、十分な給付を受けられる設計になっているかを確認する必要があります。
ワンポイントアドバイス
守りの保険を見直す際は、「ご自身の年齢や健康状態を考慮した、最新の医療技術に対応した保障」になっているかをチェックすることが大切なんですね!特に、「働けなくなったときの収入サポート」が最優先の備えとなりますから、まずは「就業不能保険」についても一度確認してみるのがおすすめですよ。小さな一歩が、将来の大きな安心につながっていくんですから…。


収入が途絶える最大のリスクとは|病気・ケガ・メンタル不調の現実
40代って、仕事でも家庭でも頼りにされて、充実した生活を送っている方もきっと多いことと思います。しかし、この時期に「万が一、働けなくなったら…」と考えたら心配になりますよね。だって、収入が途絶えたら、「医療費がかかること」以上に、ご家族の生活基盤そのものを揺るがす最大のリスクだからです。このリスクを正しく知ることは、将来への安心感につながりますよ!
「長期で働けない」状況が家計を直撃
40代が直面するリスクの最も怖い点は、「病気やケガで治療費がかかること」よりも、「給与という安定した収入がストップしてしまうこと」ではないでしょうか?
現代の医療は進歩していますから、多くの病気は治る可能性が高くなっています。しかし、治療のために「長期間の休養」が必要になった場合、家計には以下のようなダブルパンチが襲いかかります。
- 収入のストップ(または大幅な減少)
- 毎月の生活費、住宅ローン、教育費の支払いが難しくなる。
- 支出の増加
- 治療費や入院雑費などが重なり、貯蓄が急速に減ってしまう。
特に40代は、住宅ローンや子どもの教育費といった「毎月必ず出ていく大きな固定費」を抱えているケースが多いので、収入の途絶はまさに一大事なんです。
増加する「病気・ケガ」以外のリスク
以前は「収入途絶」といえば、がんや心疾患といった「三大疾病」が主な原因とされていました。もちろん、これらへの備えは必須です。しかし、近年、40代の働く世代で「休職の原因」として増加傾向にあるのが「メンタルヘルス不調」なんです…。
| リスクの種類 | 40代の現実 | 必要な休養期間の傾向 |
|---|---|---|
| 病気 | がんや生活習慣病(高血圧・糖尿病など)の発症リスク増 | 治療内容により短期〜長期 |
| ケガ | スポーツやレジャー中の事故、突発的な骨折など | 程度によるが、数か月の休養も |
| メンタル不調 | ストレスや過労によるうつ病、適応障害など | 長期化しやすく、社会復帰に時間がかかる傾向 |
特にメンタル不調は、外見からはわかりにくい上に、回復まで半年~数年かかることも珍しくありません。この「長期の休職」こそ、40代の家計にとって最も警戒すべきリスクの一つなんですね。
公的保障制度の「落とし穴」を知っておこう
「会社員だから傷病手当金があるし大丈夫!」と思われるかもしれません。確かに傷病手当金は心強い制度です。しかし、実は十分ではない点もあります。
- 給付期間の限界
- 最長1年6ヶ月まで、という期限があります。それ以降は、ご自身の貯蓄や別の公的制度(障害年金など)に頼らざるを得ません。
- 給付額の限界
- 概ね標準報酬日額の3分の2程度です。つまり、毎月の給料の全額はカバーされないんですね。給付額が減っても、住宅ローンや教育費の支払額は変わりません。
この「公的保障で足りない部分」を、民間保険である「就業不能保険」などで埋めることが、守りの保険の最大の目的になるんです。
ワンポイントアドバイス
収入途絶のリスクに備える際、一番に考えていただきたいのは「毎月の固定費(住宅ローンや子どもの習い事など)」なんですね!まずは、それらが途絶えることなく支払い続けられるかを基準に、必要な保障額を逆算してみましょう。「収入ダウンの金額」ではなく「毎月必要な生活費」をカバーできる仕組みを作ることが、不安を安心に変える一番の近道なんですから…。


医療保険の見直しポイント|入院・手術・通院のカバー範囲を確認しよう
40代になって、健康診断の結果が少し気になり始めた…という方もいらっしゃるかもしれませんね。体調管理に気をつけていても、突然の病気やケガは、誰にでも起こり得るもの。だからこそ、「もしもの時に経済的な不安を感じずに、安心して治療に専念できる」ように、医療保険を整えておくことが大切なんです。今の時代に合った保障になっているか、一緒に楽しく確認していきましょう!
時代の変化に合わせた「入院」の考え方
ひと昔前の医療保険は、「入院日数」が長ければ長いほど保障が手厚いものが主流でした。しかし、今の医療は大きく変わっています。
- 入院日数の短期化
- 医療技術の進歩により、多くの病気で入院期間は短くなっています。厚生労働省のデータを見ても、平均在院日数はどんどん短くなる傾向にあるんですね。
- 「日帰り」や「短期入院」での手術増加
- 前は数日入院が必要だった手術も、現在では日帰りで済むケースが増えています。
この変化に合わせて、医療保険を見直すときに大事なのは、「日額いくら」という考え方だけでなく、「短期入院や日帰り手術にも対応できているか」をチェックすることなんです。
40代が特に注目すべき3つの保障
医療保険の見直しで、40代の皆さんに特に注目してほしいのは、以下の3つのポイントです。
1,手術給付金と対象範囲
- チェックポイント
- 手術給付金が、公的医療保険の対象となる手術全般を広くカバーしているか。
- 重要性
- 最新の治療技術には、「内視鏡手術」や「カテーテル手術」など、体への負担が少なく短期で済むものが含まれます。これらが給付金の対象になっているかを確認しましょう。
2,通院給付金(退院後の通院)
- チェックポイント
- 退院後の通院までサポートする特約が付いているか、または追加できるか。
- 重要性
- 入院が短くなった分、退院後にリハビリや経過観察で通院する回数が増える傾向にあります。この通院にかかる費用をカバーできると、治療後の生活がグッと楽になるんですよ
3,先進医療特約
- チェックポイント
- 先進医療の技術料(全額自己負担)を全額カバーできる特約が付いているか。
- 重要性
- 先進医療は、公的医療保険の対象外のため、費用が数百万円になることもあります。この特約があれば、費用を心配せずに最新の治療を受ける選択肢が持てるんですね
| 40代に必要な医療保障の進化 | 従来の保険(〜30代) | 最新の保険で強化したい点 |
|---|---|---|
| 入院 | 長期入院の日額給付 | 短期入院・日帰り手術への対応 |
| 手術 | 入院を伴う大きな手術が中心 | 内視鏡・カテーテルなど幅広い手術のカバー |
| 通院 | あまり重視されない傾向 | 退院後の通院をカバーする特約 |
医療費の自己負担を軽減する工夫
医療保険の保障を考えるときに、必ず思い出してほしいのが「高額療養費制度」です。これは、月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が戻ってくる国の制度なんですね。
つまり、医療保険で「公的制度でカバーしきれない部分」を重点的に補う、という考え方が賢い設計術なんです。
- 一時的な自己負担: 高額療養費が戻ってくるまでの立て替え費用。
- 差額ベッド代: 個室などを利用した場合の全額自己負担になる費用。
- 食事代: 入院中の自己負担になる費用。
医療保険は、これらの「公的制度のスキマ」を埋めて、ご自身の貯蓄を守るための大切な道具だと思ってくださいね!
ワンポイントアドバイス
今の医療保険が古いと感じたら、まずは「保障の期間」を見直しましょう!終身医療保険(一生涯の保障)であれば安心ですが、もし定期型(期間が決まっている)であれば、40代のうちに終身型への切り替えを検討するチャンスなんですね。若いうちに切り替えれば保険料も抑えられますし、一生涯の安心を手に入れることができますよ!
こんな記事も読んでみてね!
就業不能保険で生活を守る|働けない期間の収入をどう補うか
40代の皆さんは、一家の大黒柱として、毎日本当にお疲れ様です!。ご自身の健康には気をつけていても、人生には予期せぬ出来事が起こるものです。「病気やケガで、もし長期間働けなくなったらどうしよう…」という不安は、特に責任感の強い40代の方ほど、大きく感じるのではないでしょうか。でも、安心してください。この不安を「安心」に変えるための心強い味方が、「就業不能保険」なんです。これを活用すれば、万が一の時も家計の安定を守りながら、治療に集中できる前向きな環境を作ることができるんですよ!
医療保険と就業不能保険の違い
「入院したら医療保険があるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、実は医療保険と就業不能保険は、守る目的が異なります。
| 保険の種類 | 守る目的(お金の用途) | 給付の対象 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 「医療費」の支払い | 入院、手術、通院などの治療費 |
| 就業不能保険 | 「生活費」の支払い | 働けない期間の失われた収入 |
医療保険が「治療の費用」をカバーするのに対し、就業不能保険は「日々の生活費(家賃・ローン・食費・教育費など)」をカバーします。つまり、家計の安定という点で、就業不能保険は40代の「守りの保険」の要だと言えるんですね。
公的制度の「タイムリミット」を超える安心
会社員の方には「傷病手当金」という、働けない期間の収入を補う公的な制度がありますね。これはとてもありがたい制度です。しかし、前述の通り、これには「タイムリミット」があります。
- 傷病手当金は最長1年6ヶ月
- 給付額は月収の約3分の2
現代では、特にメンタル不調や一部のがん治療などで、治療が長期化し、復職まで1年半以上かかるケースも少なくありません。就業不能保険は、この公的制度の保障期間が終わった後も、給付金を継続して受け取れる安心感を提供してくれます。
つまり、長期にわたる療養になっても、「生活のためにお金を切り崩す」という心配から解放され、安心して治療に専念できる環境を整えることができるんです。
就業不能保険を設計する3つのポイント
就業不能保険に加入する際に、賢く、「備えすぎない」ように設計するためのポイントがこちらです。
- 必要な月額給付金を決める
- 毎月の生活費から、公的保障(傷病手当金など)でカバーできる金額を差し引いた、「本当に不足する金額」を設定しましょう。無理のない保険料で済みます。
- 給付金の支払い開始時期(免責期間)を決める
- 多くの商品では、働けなくなってから60日や180日など、給付金が始まるまでの期間(免責期間)を選べます。この免責期間中は、ご自身の貯蓄や傷病手当金で対応し、保険料を抑える工夫もできますよ。
- 保障の終了年齢を決める
- 定年退職を迎える60歳や65歳など、ご自身のライフプランに合わせて設定しましょう。長くしすぎると保険料が高くなるため、「働いて収入を得る期間」を明確にしておくことが大切です。
ワンポイントアドバイス
就業不能保険を選ぶ際は、「ご自身が働けなくなる原因」のカバー範囲をチェックしましょう!特に「精神疾患(メンタル不調)」による就業不能まで保障の対象に含まれているかどうかが、40代の方にとって非常に重要なポイントなんですね。この保障があれば、心の健康を崩してしまった時でも、経済的な心配をせずにじっくりと休養することができますよ!
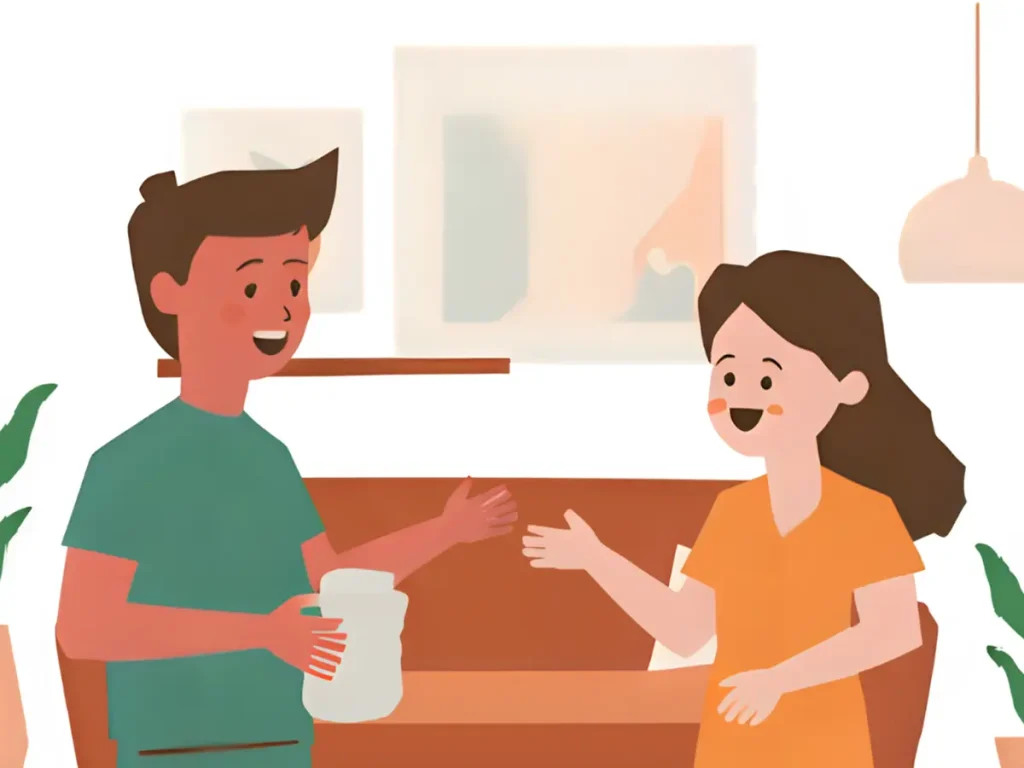
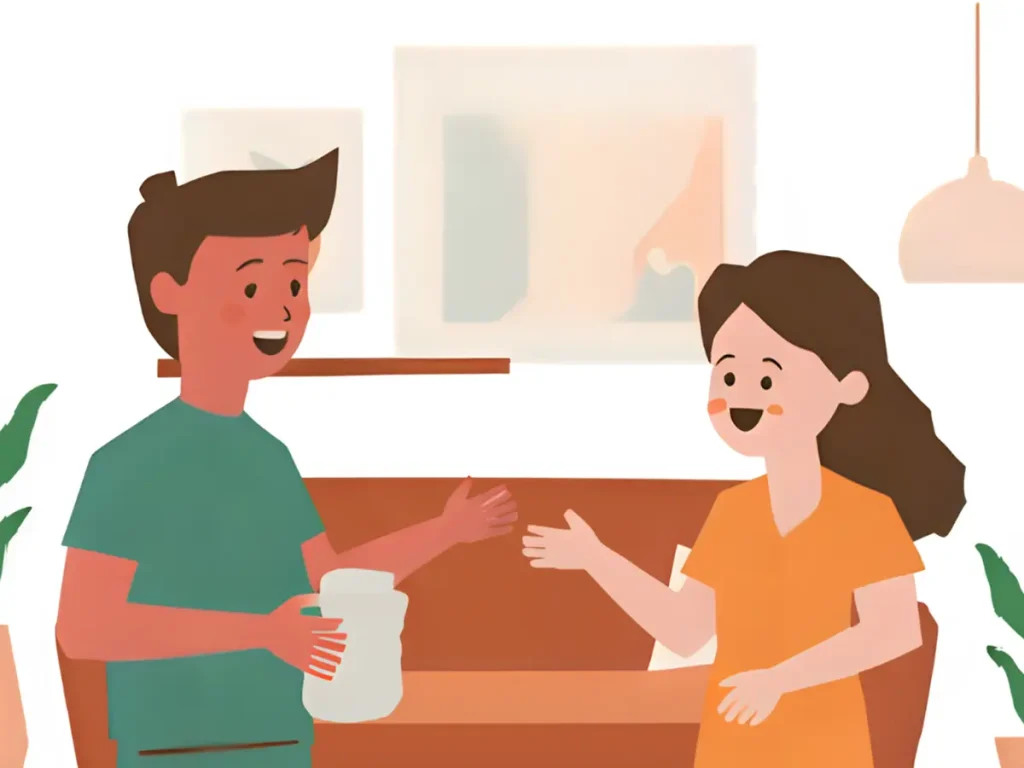


がん保険の選び方|40代が意識すべき治療費と長期化リスク
がんは「治る病気」へと変化しています!大切なのは、治療の途中で経済的な心配をしないための準備です。備えを万全にしておくことで、「もしも」の時に最善の治療を選択し、前向きな気持ちで治療に専念できる環境を整えることができますよ!
40代の「がん治療」における2つの大きな経済的リスク
40代の方ががん保険を考える上で、特に意識してほしいのは、治療費そのものよりも、「治療が長期化すること」と「治療の多様化」に伴う費用です。
治療の長期化と「逸失利益(収入減)」
がんは、すぐに終わる病気ではなく、診断、手術、そして通院による抗がん剤治療や放射線治療と、治療期間が長期化するケースが多くなっています。
- 治療の長期化
- 診断から社会復帰まで、数年単位で時間がかかることも珍しくありません。
- 収入の不安定化
- 長期にわたる通院や体調不良で、仕事のセーブや休職が必要になり、収入が減ってしまうリスクが継続します。
がん保険の給付金を、治療費だけでなく、この収入減を補うための生活費としても活用することが大切なんですね。
最新の治療にかかる全額自己負担の費用
日本の公的医療制度は素晴らしいですが、すべてのがん治療をカバーするわけではありません。
- 先進医療費
- 厚生労働大臣が定める先進医療にかかる費用は、全額自己負担となります。非常に高額になるケースもあります。
- 自由診療
- 国内未承認の抗がん剤や免疫療法など、最先端の治療を望んだ場合、これも全額自己負担になります。
40代にフィットするがん保険の「3大チェックポイント」
今の時代のがん治療に対応できる保険を選ぶために、次の3つをチェックしましょう。
1,一時金(診断給付金)の有無と金額
- なぜ重要か
- がんと診断された直後にまとまったお金を受け取れるのが一時金です。治療が始まる前の準備費用や、公的医療保険外の治療費に充てる自由度の高い資金として、最も重要です。
- 選び方の目安
- 100万円~300万円程度を、ご自身の貯蓄状況と照らし合わせて検討しましょう。一時金を複数回受け取れるタイプだと、再発・転移にも備えられて安心です。
2,通院・抗がん剤治療への備え
- なぜ重要か
- 医療の進歩により、入院よりも通院で治療を続けるケースが増えています。
- チェックポイント
- 抗がん剤治療や放射線治療など、「退院後の通院治療」に対して、回数や期間に制限なく給付される保障が付いているかを確認しましょう。
3,上皮内新生物の取り扱い
- なぜ重要か
- 上皮内新生物(初期のがん)は、悪性度が低いとされ、通常の悪性新生物と区別されることがあります。
- チェックポイント
- 保険会社によって、上皮内新生物の場合、一時金が減額されたり、給付対象外になるケースがあります。初期の段階からしっかり保障を受けられる商品を選びたいですね。
必要な保障従来の保険40代で強化すべき点一時金入院を伴う治療開始時診断直後のまとまった資金治療費入院日額給付が中心通院での抗がん剤・放射線治療の保障特約なし、または不十分先進医療特約は必須級
ワンポイントアドバイス
がん保険は、健康なうちにしか加入できません。40代で健康状態が比較的安定している今のうちに加入すれば、終身保障(一生涯の保障)を比較的安い保険料で確保できる大きなメリットががあるんですね!少しでも早く検討することが、将来の経済的な負担を減らす一番の対策になりますよ!




貯蓄と保険のバランス|「備えすぎ」にならない賢い設計術
一生懸命働いて得た大切なお給料から払う保険料…。せっかく安心のために加入するのに、「毎月の支払いが家計の重荷になってしまう…」なんてことになったら、少し残念ですよね・・。40代が目指すべきは、「貯蓄」と「保険」がお互いの弱点を補い合う、賢くバランスの取れた設計なんです!必要な備えをしっかり確保しつつ、保険料を抑えて貯蓄に回す余裕を作ることが、未来の大きな安心につながりますよ!
貯蓄と保険、「任せる役割」を明確にしよう
「備えすぎ」になる最大の原因は、「貯蓄で賄えること」まで保険に頼ろうとしてしまうことなんですね。まず、万が一のリスクを、ご自身の「貯蓄」で対応できるものと、「保険」の力が必要なものに分けることから始めましょう。
- 貯蓄が担うべき役割
- 緊急予備資金: 3ヶ月〜6ヶ月程度の生活費(突発的な修理費、短期入院の自己負担など)。
- 短期的な費用: 高額療養費制度を利用した後の「少額の医療費」や「一時的な差額ベッド代」など。
- 保険が担うべき役割(保険の得意分野)
- 収入の途絶(長期): 病気やケガで数年単位で働けない期間の生活費(就業不能保険)。
- 超高額の医療費: 数百万円かかる先進医療や、自由診療の治療費(がん保険特約、医療保険特約)。
- 一家の大黒柱の死亡: 遺された家族が経済的に自立するまでの生活費や教育費(死亡保険)。
つまり、「貯蓄ではとても対応できない、家計を揺るがす巨大なリスク」に狙いを絞って保険をかけるのが、賢い設計術なんですね。
| リスクの規模 | 対応策 | 目的 |
|---|---|---|
| 小規模 | 貯蓄(緊急予備資金) | 短期的な医療費、生活費の立て替え |
| 大規模 | 保険(保障型) | 収入の長期途絶、数千万円の必要資金 |
保険料を最適化する「3つの引き算」設計術
「備えすぎ」を防ぎ、保険料を最適化するために、必要な保障額から以下の要素を「引き算」することを意識しましょう。
1,公的保障の引き算
会社員の方であれば「傷病手当金」、誰でも使える「高額療養費制度」など、公的制度でカバーされる部分を計算から除外しましょう。
2,貯蓄の引き算
死亡保障を考える際、もしもの時に使える「現在の貯蓄額」や「退職金」を、必要な保障額から差し引きます。
3,医療の引き算
- 入院日額は、差額ベッド代を考慮しつつも、高額療養費制度があるため、最低限の日額(例:5,000円〜7,000円)に抑える工夫ができます。
- 保障を「掛け捨て型」にすることで、毎月の保険料を大幅に抑えることができます。抑えた分を資産形成に回せますね。
保険は「最大のリスク」をカバーするものと割り切り、保険料を抑えて、余裕ができた分のお金は将来のために貯蓄や資産運用に回す。これが、40代の皆さんが最も前向きになれるお金の守り方なんです。
賢く設計するための「掛け捨て型」活用術
保険料の無駄を省き、貯蓄と両立させるには、掛け捨て型の「保障性保険」をメインに活用するのが効果的です。
| 保険の種類 | 特徴 | 40代における役割 |
|---|---|---|
| 保障性(掛け捨て) | 満期保険金はないが、保険料が安い。 | 必要な期間・必要な保障を格安で確保し、家計を守る。 |
| 貯蓄性(貯蓄型) | 満期保険金や解約返戻金がある。 | 保険料が高くなりがちで、資金効率が悪い可能性も。 |
貯蓄性を保険に求めず、保障は安く、お金を増やすのは貯蓄や投資でと役割分担をすることで、バランスの取れた設計が完成します。
ワンポイントアドバイス
家計に無理なく保険を続けるための目安として、「毎月の保険料は、手取り月収の5%程度」に収まっているかを確認してみましょう!もしこれを超えているようであれば、「備えすぎ」かもしれません。保険は「安心を買うもの」ですが、家計が苦しくならないことが、最高の安心につながるんですね!
こんな記事も読んでみてね!
夫婦・家庭で考えるリスク対策|収入と支出を見える化して守る家計
40代の家計にとって、「見えないお金の流れ」は大きなリスクになります。なぜなら、支出の全体像がつかめないと、本当に必要な備えが見えなくなってしまうからなんですね!つまり、家計を守る第一歩は「収入と支出の見える化」なんですね。ここでは、夫婦や家族で協力して“リスクに強い家計”を作るコツをご紹介します。
家計のリスクは「共有」で減らせる
特筆すべきは、家計のリスクは「一人で抱え込まないこと」で大きく減らせるという点です。夫婦で家計の状況を共有すれば、急な出費にも柔軟に対応できます。
📌 たとえば、次のような話し合いをしておくと安心です。
- 月々の固定費(住宅ローン・保険・通信費)を一覧化
- どの口座から、何が引き落とされているかを整理
- 万が一の時、どのくらいの生活費を維持できるか確認
意外にも、こうした“共有の時間”がリスク対策の第一歩なんです。お金の話をオープンにすることで、お互いの安心感も高まりますよ。
支出を「目的別」に整理する
注目すべきは、支出を“目的ごとに分ける”こと。一見面倒に感じるかもしれませんが、これが家計を守る最大のコツです。
| 支出の区分 | 主な内容 | 見直しポイント |
|---|---|---|
| 生活固定費 | 家賃・光熱費・保険料など | 無駄な固定契約がないか |
| 変動費 | 食費・レジャー・教育費など | 月の上限を決める |
| 貯蓄・備え費 | 貯金・保険・投資など | バランスを年1回確認 |
こうして整理するだけで、「使いすぎ」と「備えすぎ」の両方を防げます。
つまり、支出の見える化は“安心の土台づくり”そのものなんですね。
「夫婦チーム」で守る家計習慣
家計の管理は、どちらか一方に任せず「チーム戦」で考えるのが理想です。それぞれの得意分野を活かせば、無理なく続けられます。
- 夫:収入や保険の確認、長期のライフプラン設計
- 妻:日々の支出管理、生活費の最適化
- 一緒に:将来のイベント費(教育・老後など)の目標設定
言い換えれば、「家計を見える化すること」は、夫婦の信頼を深めるきっかけにもなるんです。
ワンポイントアドバイス
家計のリスク対策で大切なのは、“完璧に管理すること”ではなく、“続けられる仕組み”を作ること。
家計簿アプリや共有スプレッドシートを使えば、夫婦で簡単に「家計の見える化」ができますよ。
つまり、「話せる家計」こそが、いざという時に強い家計なんです。




今すぐできる保険の見直しステップ|安心の未来をつくる第一歩
「保険の見直し」と聞くと、「難しそう」「後回しでいいかな」と思ってしまう人も多いですよね。でも、実は40代の今こそが見直しのベストタイミング。ライフステージの変化や収入の波をふまえ、「今の自分たちに合った保険」に整えることで、無駄を省きながら安心を強くできるんです!
ステップ1:現在の保険内容を「整理」する
まずは今加入している保険をすべて書き出してみましょう。どんなに小さな保険でも、「把握すること」からすべてが始まります。
📌 一覧表にまとめておくと、後で比較しやすくなります。
| 保険の種類 | 保険会社 | 月額保険料 | 主な保障内容 | 満期・更新時期 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険 | ○○生命 | 6,000円 | 入院1日5,000円、通院保障あり | 2030年3月 |
| がん保険 | △△保険 | 4,000円 | 診断一時金100万円 | 終身 |
| 就業不能保険 | □□損保 | 3,500円 | 収入補償月10万円 | 2040年まで |
この表を作るだけでも、「あれ? 似たような保障が重なってる」「更新型で将来保険料が上がるかも」といった発見があるはずです。
ステップ2:家族構成と生活費から「必要保障額」を確認
次に、「万一のとき、いくら必要なのか」を把握しましょう。大切なのは、「なんとなく」ではなく「数字で」考えることです。
📌 確認しておきたいポイントは以下の通りです。
- 毎月の生活費(住居費・教育費・食費など)
- 貯蓄額・預金額
- 今後のライフイベント(子どもの進学・住宅ローン完済時期など)
これをもとに「どんなときに、どのくらいの金額が必要か」を整理しておくと、保険の過不足が一目で分かります。たとえば、共働き家庭なら「どちらかが働けなくなっても家計がまわるか」という視点で見直すのもポイントです。
ステップ3:不要な保障を減らし、足りない部分を補う
「整理」と「必要額の確認」が終わったら、いよいよ見直しの本番です。見直しのコツは、「減らす」「守る」「足す」の3ステップで考えること。
- 減らす:重複している保障(例:医療保険+共済)を整理
- 守る:生活に直結する保障(医療・収入補償)は残す
- 足す:今のリスクに合わせて新しく追加(例:就業不能・がん長期治療)
とくに40代は「収入を守る」ことが最重要。収入補償型の保険を追加しておくと、病気やケガで働けない期間も安心が続きます。
ステップ4:定期的な「棚卸し」でムダを防ぐ
保険は「入って終わり」ではなく、「定期的に見直す」ことで価値が続きます。おすすめは、1〜2年に一度のチェック。たとえば以下のような変化があったときは、必ず再確認してみましょう。
- 住宅ローンを組んだ・完済した
- 子どもが独立した
- 転職・退職などで収入が変わった
- 健康状態が変わった
これらを見逃すと、必要のない保障を払い続けることにも…。家計簿アプリや保険管理アプリを使えば、定期見直しもラクになりますよ。
ワンポイントアドバイス
保険の見直しは「大きく変える」よりも、「少し整える」気持ちで始めるのが成功のコツです。とくに40代は、家計もライフプランも変化の多い時期。まずは「今ある保険を可視化する」だけでも大きな前進です。
そして、見直しの際は1社だけでなく複数の保険会社を比較することをおすすめします。保障内容や保険料の差が、安心と節約の両立につながります。保険の見直しは“未来へのメンテナンス”。焦らず一歩ずつ進めれば、数年後には「見直してよかった」と心から思えるはずですよ。




今すぐ解決!40代にベストな保険に関する15の疑問
40代は、まだまだ現役で働き盛りの時期。しかし同時に、体の変化や家族の将来など、「守るべきもの」が増えてくる年代でもあります。だからこそ、「もしも」のときに生活を支えてくれる保険の準備が欠かせません。医療保険で治療費を、就業不能保険で収入を、そしてがん保険で長期の療養リスクをカバーすることで、経済的な不安を大幅に減らすことができます。
大切なのは、“入りっぱなし”にしないこと。ライフステージに合わせて定期的に見直すことで、ムダを省きながら本当に必要な保障を確保できます。今日の小さな行動が、未来の大きな安心につながります。まずは一度、自分と家族の「守りの保険」をチェックしてみましょう。
「それ、40代ではNGかも?」——今さら聞けない“大人のマナー”、ちゃんと身についていますか?
年齢を重ねるごとに、周囲の見る目も自然と変わってくるもの。ビジネスでもプライベートでも、ちょっとした振る舞いがあなたの印象を大きく左右します。
「え、そんなこともマナーなの?」と思わずドキッとする内容も盛りだくさん!
40代の今だからこそ押さえておきたいマナーをわかりやすくまとめました。
気になる方は、こちらの記事をぜひ読んでみてくださいね。